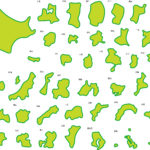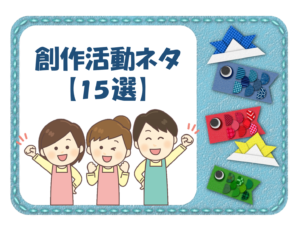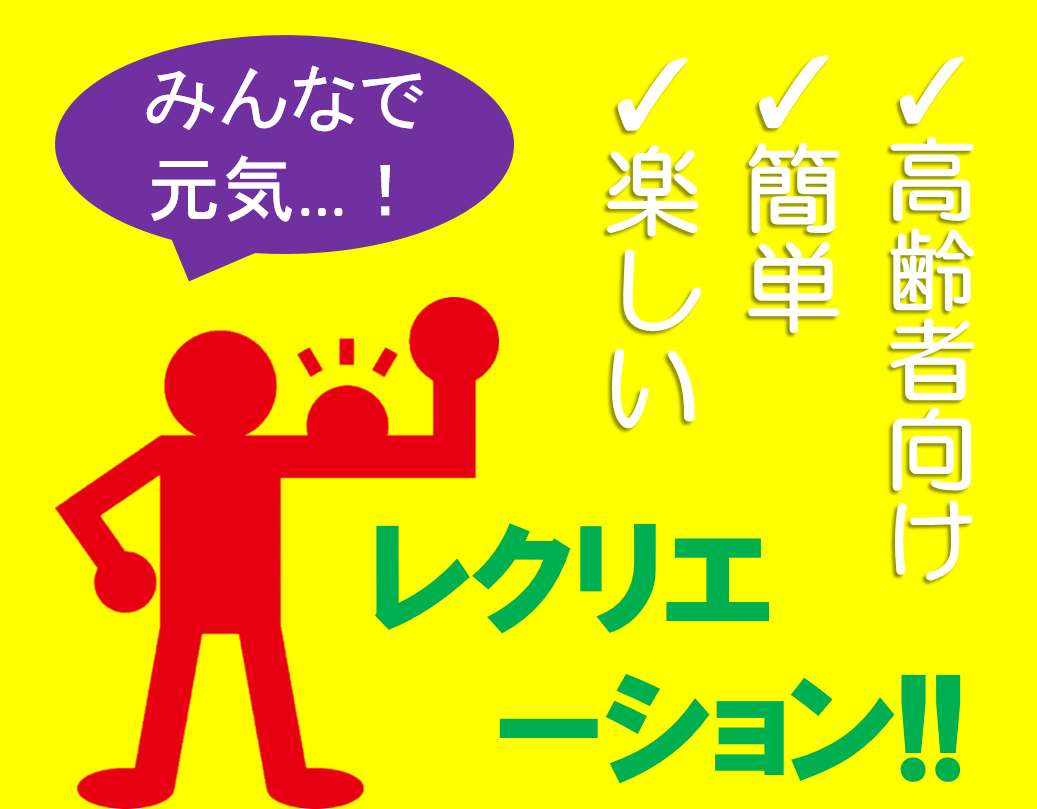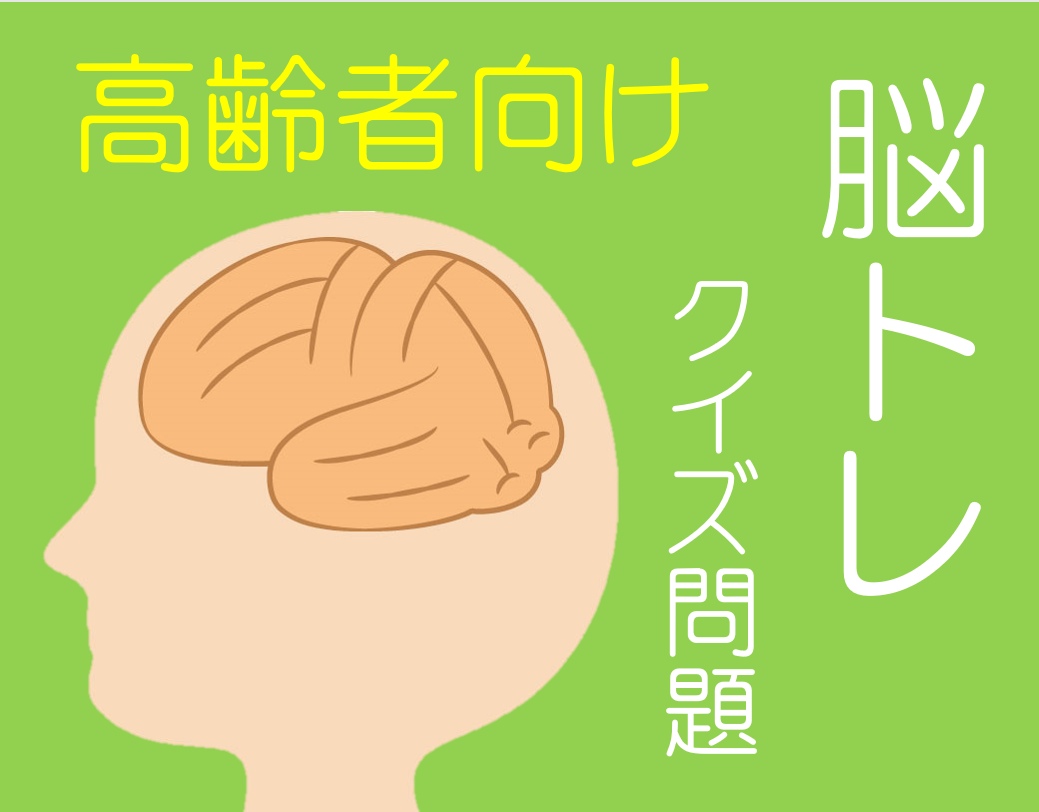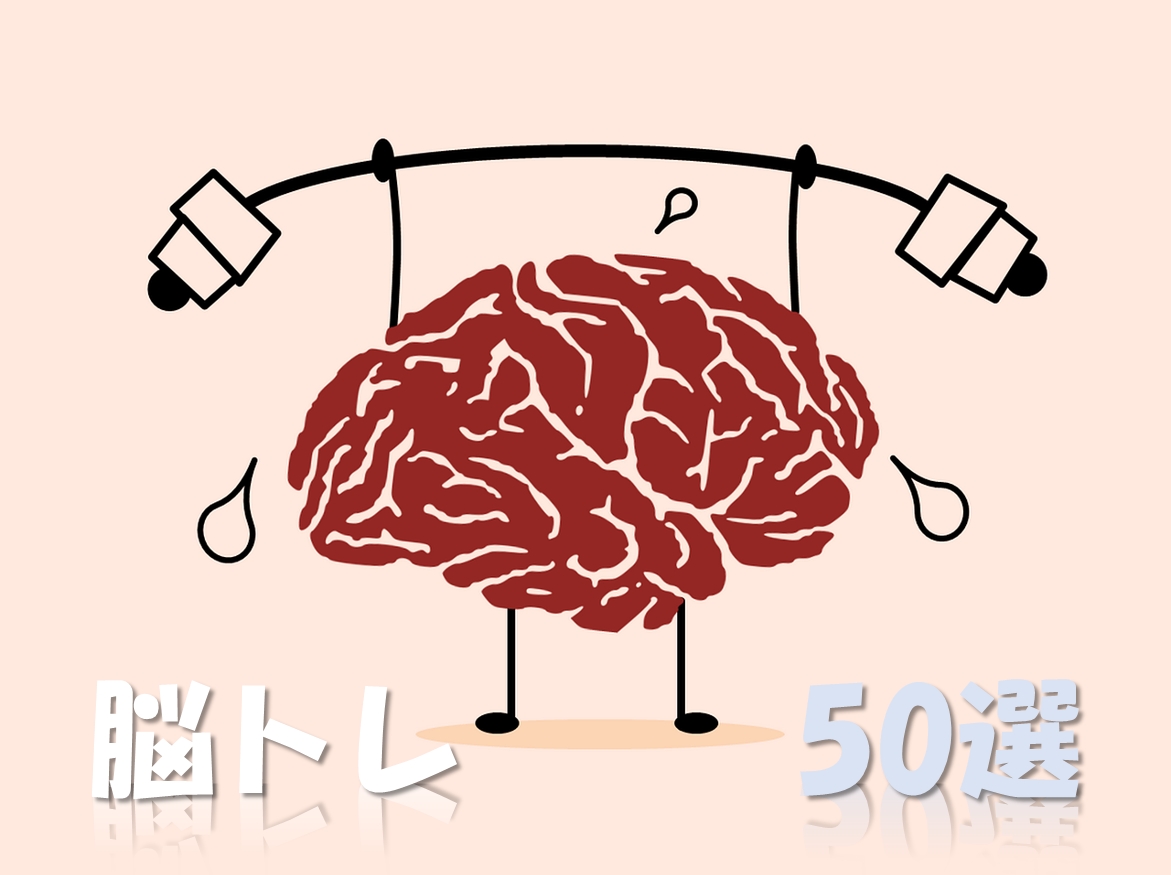(※2018.11.14に20選へ変更しました)
今回は聴覚に障害を持っている方にお勧めのレクリエーションを紹介します。
聴覚障害と一言で言っても、その障害の程度は様々です。
例えば高齢者。
高齢者の多くは加齢(後天的)とともに難聴になっていきます。
特に高音になるほど聞きにくくなり、耳元で大きな声でゆっくりとお声かけしないと、こちらがお伝えしたいことが伝わりにくくなります。
しかし、この聴覚の障害の場合、元々元気な頃は支障なく耳が聞こえていた方がほとんどです。
ですので、ほかの高齢者と一緒のレクリエーションを行なった場合、多少の不便を感じたとしても職員が耳元で説明をすることで行なえたりもします。
一方、生まれながら(先天的)にして聴覚に障害がある方は同じようにはいきません。
特に耳からの情報が一番大きい合唱などは難しいと思いますし、何をされているのかわからない方もいらっしゃいます。
しかし、聴覚障害者だけ別のレクリエーションを行なうのは一緒の空間にいながら疎外感を感じさせてしまうことになります。
そこで今回は、聴覚障害者もそうでない方も一緒に楽しめるレクリエーション(もちろん、聴覚障害者の方だけでも楽しめます)を20種類紹介します。
目次
聴覚障害者向けレクリエーション20選

せっかく一緒の施設やデイサービスに通われているのですから、同じように楽しい時間を過ごしていただきたいですね。
①ぬり絵
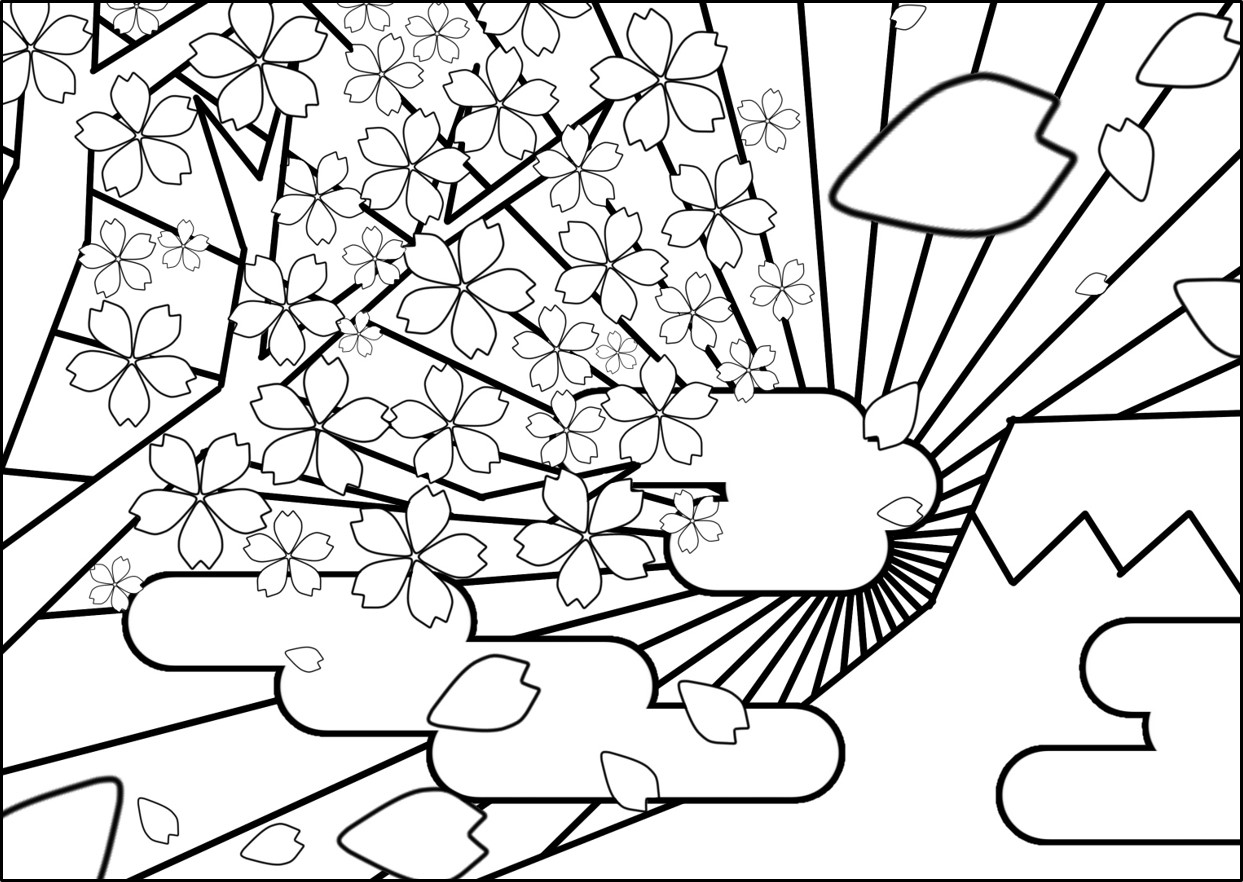
塗り絵は視覚的な情報を取り入れることが多く、あまり聴覚を必要としないため聴覚障害者の方にもストレスなく行なえると思います。
ぬり絵はご自分のペースで行なえますし、色使いもそれぞれ自由です。
綺麗に塗れている場合は拍手などのジェスチャーを使ってこちらの気持ちをお伝えしましょう。
②お手玉

こちらもお一人でできますし、大人数で「誰が長くやっていられるか?」などの競い合いもできますね。
音楽に合わせて行なうことは難しいので、職員さんが手拍子でリズムをとりながらやっていただくと、聴覚障害者の方は職員を見ながらみなさんと一緒にお手玉をすることができます。
あとは職員さんのリズム感がしっかりしていれば問題ありません。
③風船バレー

風船の行き先さえしっかり見ることができれば、聴覚障害者の方にも問題なく参加することができます。
しかし、参加者が立位で行なう場合は転倒や他の参加者との衝突などに注意が必要になりますので、できる限り座位でおこなうことをおすすめします。
こうすることで誰もが参加できるチーム戦が行なえますし、「みんなで楽しめた」という気持ちも感じていただきやすくなります。
④カードゲーム

カルタや百人一首などはじめに読み上げが必要なゲームは難しいかもしれませんが、トランプの神経衰弱やババ抜きなどはルールがシンプルシンプルですので導入しやすいですね。
また、神経衰弱などは記憶力も必要になってきますので、脳の活性化という意味でもよいかと思います。
⑤折り紙

折り紙もぬり絵などの一緒でご自分のペースで行なえるレクリエーションのひとつです。
季節や施設などの行事に合わせた折り紙を折っていただいて、それを飾ると喜んでいただけると思います。
また、折り方がわからなければ職員さんや一緒に折っている高齢者が手助けすることで、コミュニケーションも生まれますね。
⑥ジェスチャーゲーム

このゲームは口頭でお題のヒントを伝えること自体ができないゲームなので、ジェスチャーを行なう方の条件は聴覚障害者の方と一緒ですね。
たとえうまく伝えられなくてもそれが笑いになりますし、もし聴覚障害者の方がアンカーでしたら答えはホワイトボードに書いていただくなどすれば問題ありません。
みなさんで一緒に楽しめるよいゲームだと思います。
⑦肺活量サッカー

チーム対抗戦でも個人戦でも楽しむことができます。
参加者の肺活量次第です。
紙風船などをサッカーボールに見立ててテーブルを挟んで座っていただき、時間内に相手陣地にボールがいけば勝ちです。
はじめに肺活量次第と述べましたが、もし難しい方がいらっしゃればうちわなどを用いて行なってもよいと思います。
⑧ボーリング

ボールを投げることができればどなたでも参加することができます。
もし難しくても足でボールを蹴ればいいですね。
誰が一番多く倒すことができるかを競えば盛り上がりますね。
⑨体操
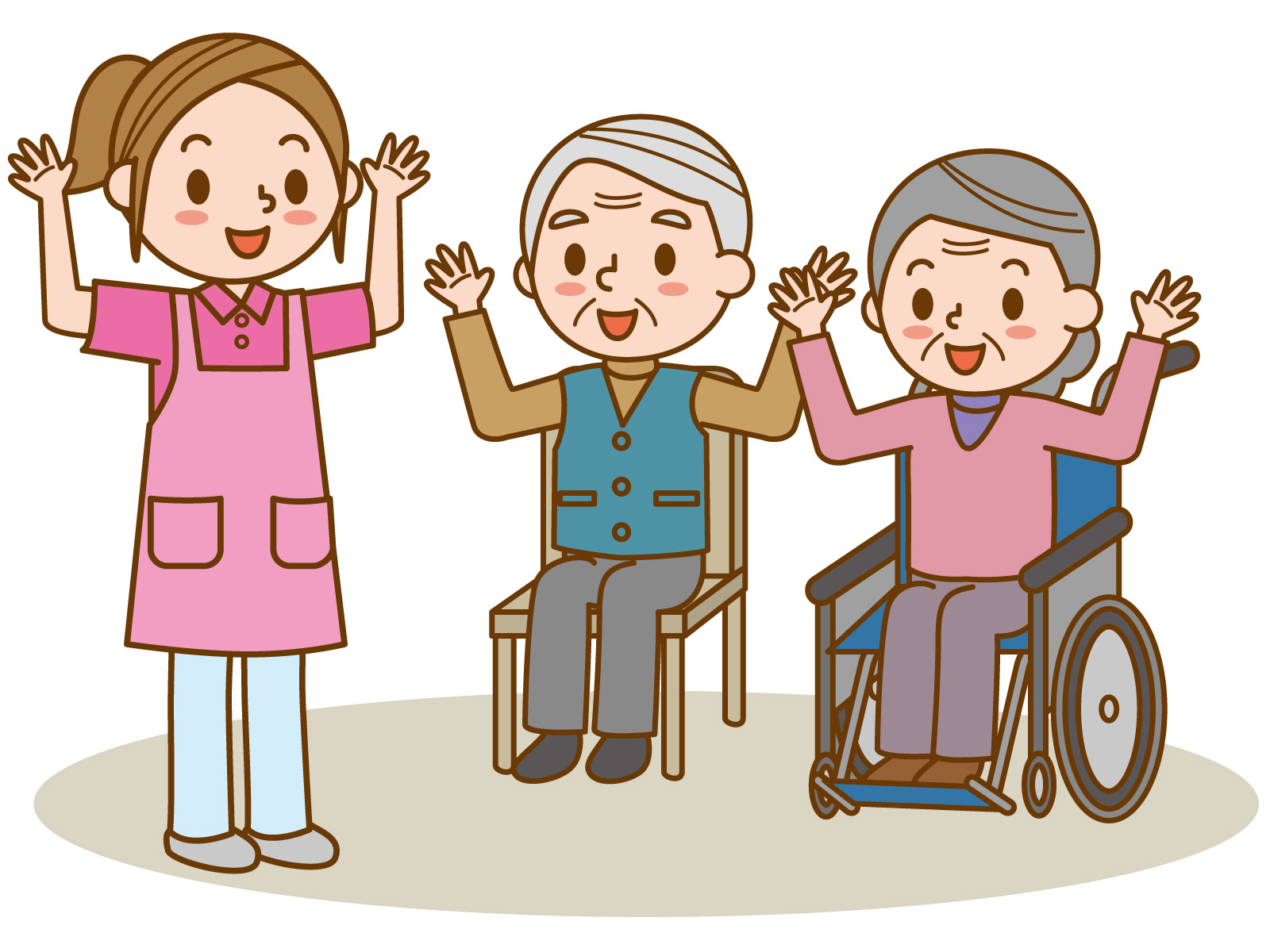
職員さんが高齢者の前で大きなジェスチャーで行なえば、聴覚障害者でも行なうことができます。
体操の内容ですが大人数で聴覚障害者に付き添えない場合は、できる限り大きな動きのものがよいと思います。
例えば、ラジオ体操などは大きな動きが多いですし、全身を無理なく動かすことができます。
職員が付き添うことができれば指体操など細かな運動も可能かと思います。
⑩〇×クイズ
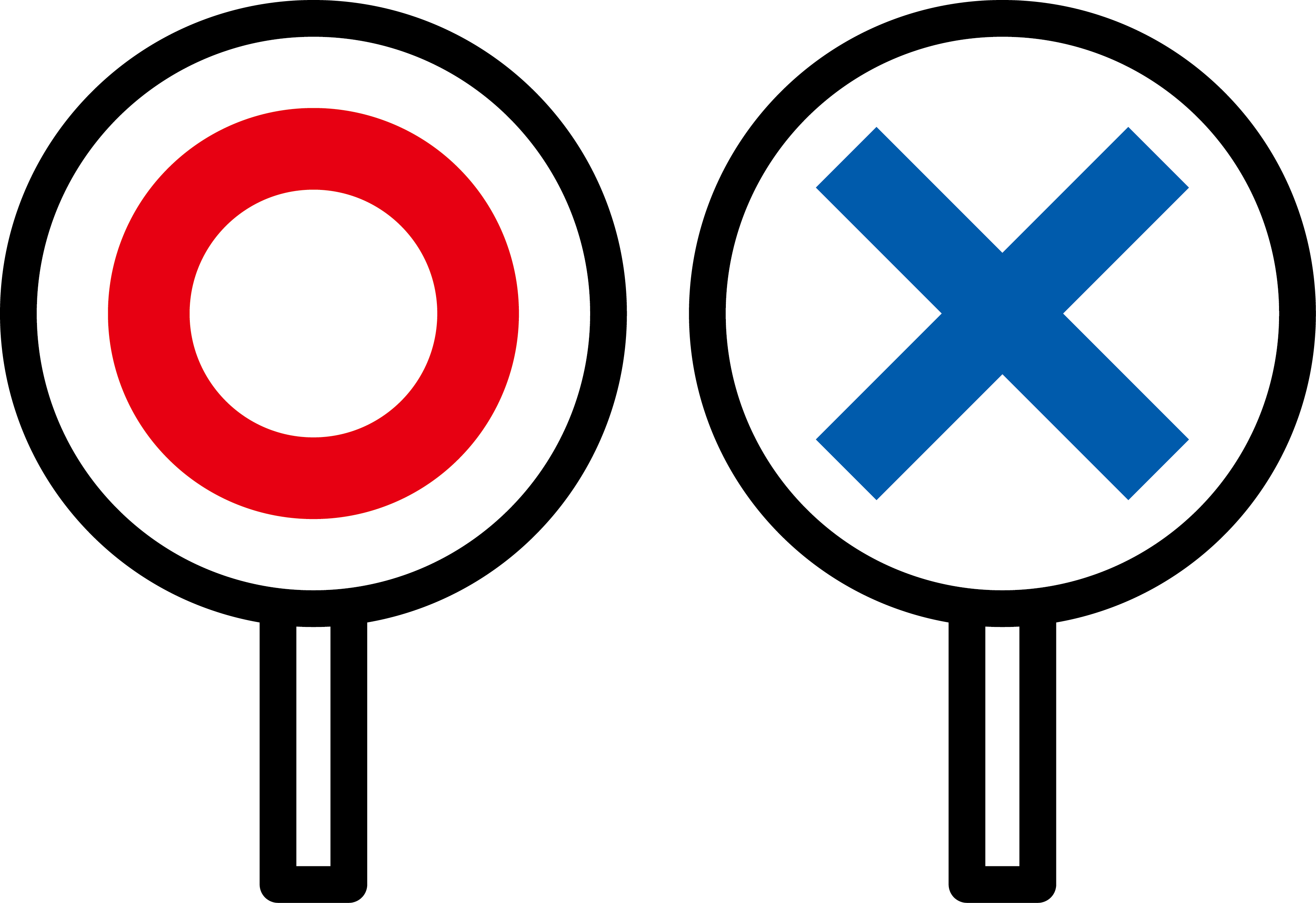
「○と思ったら右手、×と思ったら左手を挙げてください」というルールと問題文をホワイトボードに書きだせば誰でも参加が可能です。
問題文はあらかじめ紙に書いておく等準備をしていれば、間延びせずスムーズにレクリエーションが進んでいくかと思います。
⑪体内時計測定
ストップウォッチを持っていただき、職員さんが指定した時間ぴったりを狙って停止していただくゲームです。
直感に頼ったゲームなので、聴覚に依存しないゲームとしてお手軽な物の1つと言えるでしょう。
⑫玉入れ
チームに分かれて、それぞれのカゴにお手玉を投げ入れていただきましょう。
運動会の定番でもあるため、多くの方が経験していますし参加者全員が一緒に楽しみやすいゲームですよ。
⑬数字版
100個のマスに1~100までの数字を書いたマグネットシートを用意します。
小型マグネットにもそれぞれ1~100までの数字を印した物を用意してください。
開始の合図と同時に数字が一致するように、シートの上にマグネットを貼っていただき、そのタイムを競ってみましょう。脳トレにもおすすめです。
⑭棒サッカー
チームに分かれて全員が新聞紙で作った棒を持ちます。
向かい合って座っていただき、互いの足元にあるボールを棒で打って相手のゴールを狙います。
動きが目まぐるしいかと思いますが、よく見て行なえば聴覚障害があっても一緒に熱い試合に取り組むことができますよ。
⑮おはじき
テーブルの上でお手軽に楽しめる昔ながらの遊びです。
特に女性の方は得意な方が多いかもしれません。ちょっとした指先の運動としてもおすすめです。
⑯クロスワードパズル
新聞などに載っている物に日常的に取り組まれている方も多いかと思います。
個人で行なう脳トレではありますが、これも耳からの情報に依存しないので取り組みやすいでしょう。
⑰輪投げ
夏祭りなどの行事でも定番になっているゲームですよね。
普段は棒を狙っていただく基本の形で行なって、イベントごとがある時には景品に向かって輪を投げていただく形にするとより楽しめるでしょう。
⑱スリッパ飛ばし
足でスリッパを飛ばしていただくと言うシンプルなルールです。
スリッパを飛ばす先には得点を印した的を用意しておくと、単に遠くに飛ばすだけではないのでよりゲーム性が高まりますね。
立って行うのではなく、安全のためにも座って行なうようにしてください。
⑲的当て
ボールを投げて的を狙っていただくゲームです。
ボールを投げるという動きは指先や肩の運動にもなりますので、楽しみながらできる上肢の運動にもなりますね。
⑳アロマセラピー
香りで癒されるアロマセラピーは嗅覚から癒しを得られるため、聴覚からの情報に依存しないレクリエーションの1つとしてもおすすめです。
普段はなかなか経験できない癒しを感じることができるでしょう。
さいごに

いかがでしたでしょうか?
聴覚障害者にも参加できるレクリエーションを10種類紹介しました。
職員の楽しい雰囲気というのは聴覚障害者の方にも必ず伝播します。
それは耳が聞こえない分視覚で情報を集めますので、より皆さんの表情などをみているからかもしれません。
今回のレクリエーションを施設やデイサービスで実践していただき、聴覚障害者の方に楽しんでいただけたら嬉しいです。