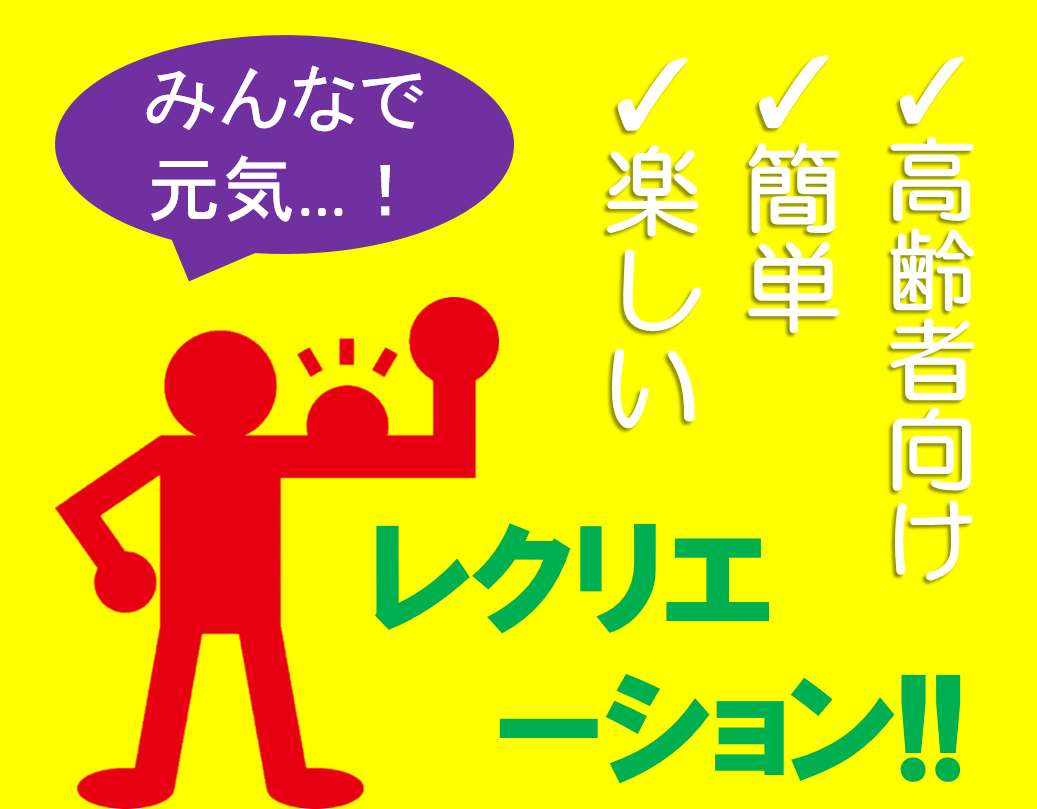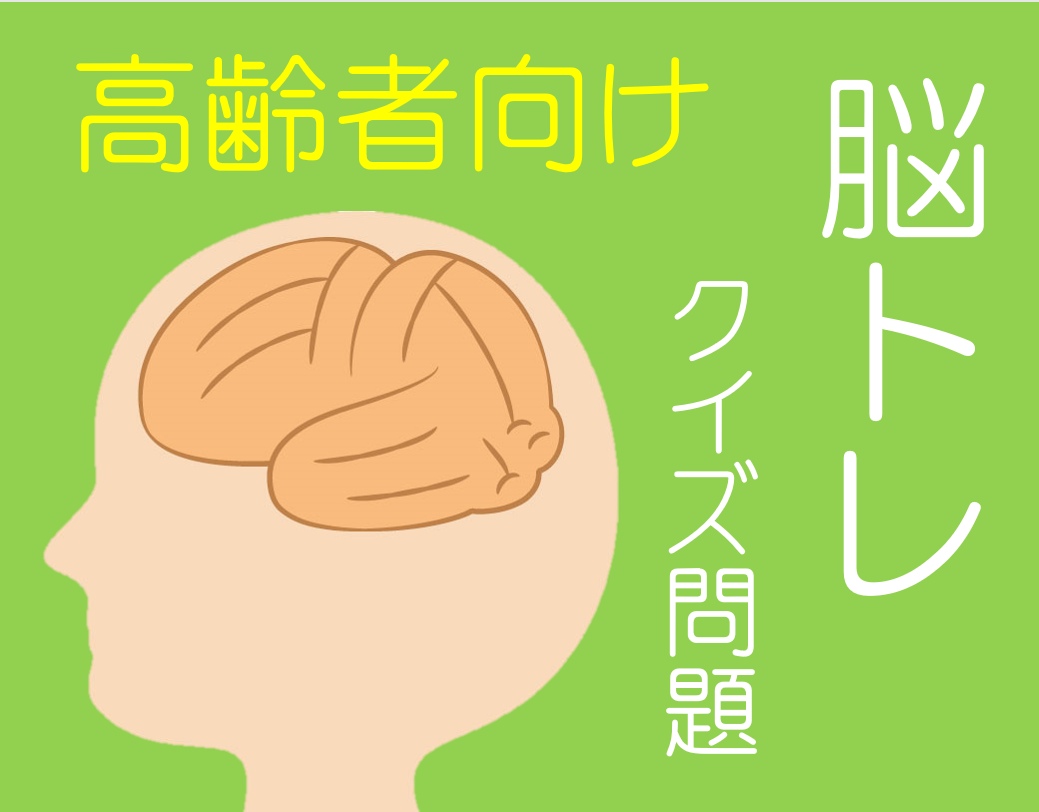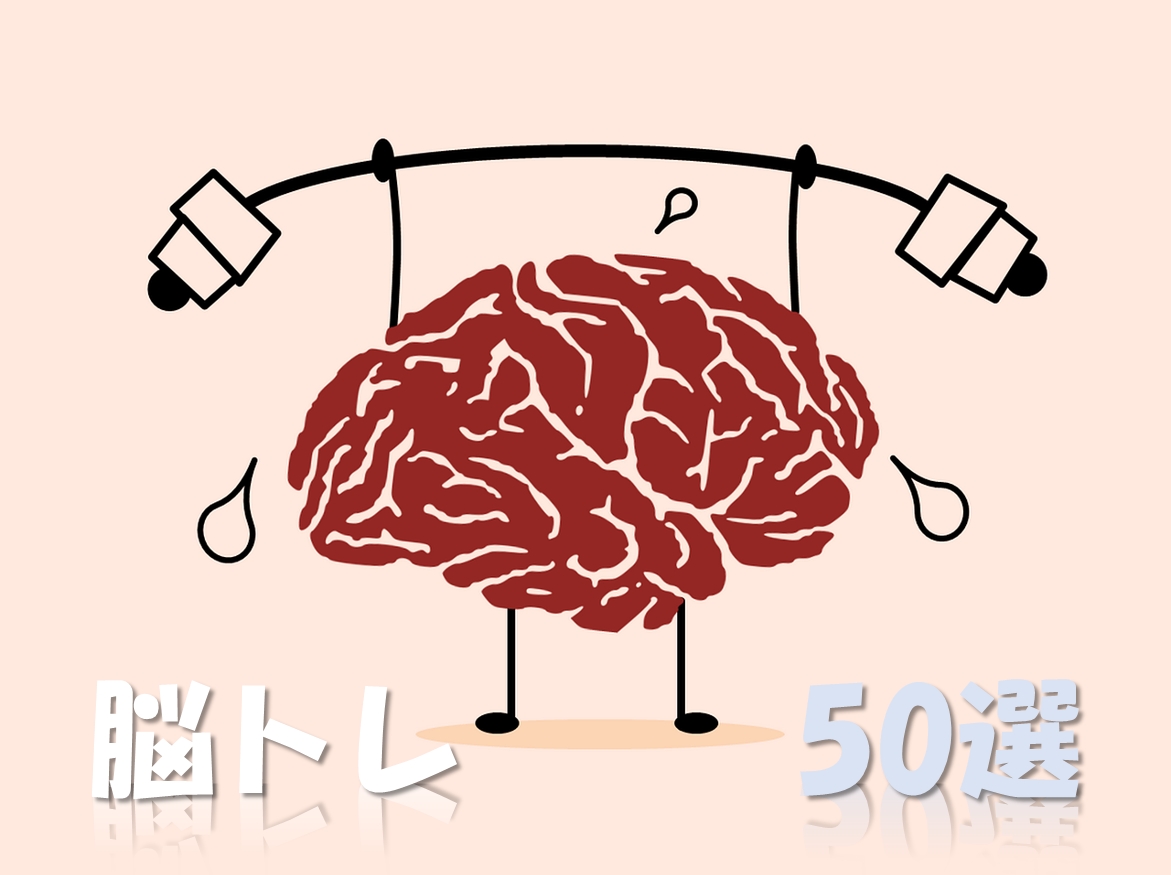今回は、9月の壁画制作におすすめの作品集をご紹介していきます。
9月は暦の上でも既に秋になったとは言え、暑い日が続くため秋と言われてもちょっと実感しにくい面もあります。
しかし、周囲に目を向けてみると徐々に秋の植物や虫も見られるようになってくる時期でもあり、まさに「小さい秋」を見つけて楽しむことができる時期でもあります。
今日から9月
秋が近づいてきたなぁとか、残暑が厳しいなとか思う今日この頃。
今月も宜しくお願いします✨ pic.twitter.com/KdRmjX1HYi— 香織🎩🐟♕💐🐻 (@Kaori_7070) September 1, 2019
十五夜のお月見も伝統的ですね。
また、敬老の日は施設でもイベントとして計画を立てているであろう大切な日なのではないでしょうか?
そこで、9月の壁画には「秋の草花などの自然に関する作品」や「敬老の日を祝う雰囲気の作品」を中心に行なうのがおすすめです。
それでは、さっそく9月のおすすめ作品集をご紹介していきます。
デイサービスの壁画レクとして、ぜひ取り入れてみてください!
目次
【高齢者向け】9月の壁面(壁画)製作作品集 15選

①おじいさん・おばあさん
端午の節句や桃の節句は子どもが主役の日であるように、敬老の日は利用者のみなさんが主役の日です。
とは言え、施設ではいつでも利用者のみなさんが主役のようなものではありますが(笑)
長年社会に貢献してきた高齢者に感謝し、長寿を祝う日ですのでこの作品は敬老の日を象徴するような壁画になるでしょう。
②鶴
「鶴は千年亀は万年」という言葉を聞いたことがあるかと思います。
その言葉から分かるとおり、長寿の象徴として縁起が良い動物とされています。
鶴と言えば折り紙でも定番の作品ではありますが、今回はちょっとアレンジした鶴です。こちらは知らない方も多いのではないでしょうか?
ちなみに野生の鶴の場合、実際の寿命は20~30年、動物園などで飼育されている個体になると長くて50年程度の寿命と言われており、人間を超える長寿とはいかないようです。
③亀
先に紹介した鶴と並んで長寿の象徴として縁起の良い動物です。
実際に亀は脊椎動物の中では最も長生きすると言われており、100年以上生きる個体も少なくはないと言われています。
過去には推定200歳のゾウガメが見つかったこともある程です。
人間だと長生きをしても流石に200歳までは到達できないでしょう。
とは言え、それくらい元気で長生きするくらいの気持ちで過ごしていただきたいものですね。
④海老
海老は、おせち料理でも定番の縁起が良い生き物です。
海老は長いヒゲ、曲がった腰を持っている見た目から「腰が曲がるまで長生きできるように」といった意味もあり長寿の象徴とされています。
海老のように腰が曲がってもまだまだ元気で過ごしていただけるように、縁起の良い海老を食事のメニューにも取り入れられたら良いですね。
⑤鯛
鯛も「めでたい」魚として、縁起が良い生き物の代表格の1つと言えます。
ちなみに真鯛が赤い理由はなんとも面白いもので、真鯛が海老や蟹を食べているためその色素によって赤くなるんだとか(*^^*)
⑥リンドウ
リンドウの花は敬老の日に贈られる花として人気の高いものです。
漢方薬に利用されることから「病気に打ち勝つ」という意味で「勝利」という花言葉がリンドウ全般に付けられました。
また、紫のリンドウには冠位十二階で紫が最高位であったことから、「高貴」という意味が込められるようになりました。
ちなみに、白のリンドウは「白寿」という花言葉であり、99歳を祝う花として親しまれています。
⑦彼岸花
田んぼ沿いの道などでも多く咲いているのを見かける彼岸花。
だいたい9月末頃から見頃を迎えます。乾燥状態が続いた後に大雨が降ると一斉に開花する現象も有名です。
そんな彼岸花ですが死や不吉なことを連想させる迷信もあり、贈り物としてはあまり好まれないという面もあります。
そのような意味の花言葉も持っていないのですが、彼岸花が持つ毒がそのようなイメージを独り歩きさせてしまったようです。
それでも秋を感じさせてくれる綺麗な花には変わりありませんね。
⑧コオロギ
秋になると聞こえてくる虫の声。
夏場に騒がしかったセミの声と入れ替わるように、夜に聞こえるようになると日中は暑くても秋になったことを感じられます。
秋の虫の声を楽しむ文化は日本には古くから根付いており、なんと平安時代には貴族たちの間でコオロギなどを捕まえて、カゴに入れて声を聞くという文化もあったのだとか(*^^*)
⑨コスモス
秋の花と言えば、やはりコスモスは外せません。綺麗に咲いている光景が様々な場所で見られますね。
コスモスと言えば「秋桜」と漢字で表記するのは若い世代も含め多くの方が知っていることでしょう。
しかし、これは当て字のようなものと知らない方も多いでしょう。
元々外来種であったコスモスには、「秋桜(あきざくら)」という和名が付けられました。昭和52年には山口百恵さんの名曲である「秋桜(コスモス)」がリリースされ、ヒットしたことで「秋桜」と書いてコスモスと読むことが広まりました。
実際にパソコンなどの検索でも、「コスモス」を変換すると「秋桜」と出ますよね。
⑩まつぼっくり
秋になると道端にもよく落ちているので、まつぼっくりを見かけると秋らしくなったと感じますね。
玩具に加工されたり、キャンプでは着火剤としても重宝されたりと、用途は限られているとは言え私たちの生活の中でも役立つ存在でもあります。
⑪ぶどう
ぶどうは8月から10月にかけて食べ頃を迎える果物です。
ぶどう狩りもこの時期に人気ですね。
近年では皮ごと食べられるシャインマスカットも大きな話題を呼びました。
秋の味覚としてぜひ、本物を口にしたいところです。
⑫秋刀魚
秋の味覚である秋刀魚。
脂がのった秋刀魚を七輪で焼いて食べる光景はフィクションでも度々描かれる秋らしい場面でもあります。
そんな秋刀魚ですが、この漢字の表記が広まったのは大正時代になってからと言われています。
読んで字のごとく、「秋に獲れる刀のような形をした魚」ということから広まっていきました。
⑬月と雲
月見は夜に、しかも晴れていなければできないので施設ではなかなか十五夜のお月見を楽しむのは難しいものです。
しかし、それも壁画であればいつでも満月を楽しむこともでき、気分だけでもお月見の雰囲気を感じていただけるでしょう。
⑭うさぎ
日本では月の模様がうさぎが餅をついている様子に見えるということで、お月見とうさぎは関係が深い動物として親しまれてきました。
先に述べた月と一緒に並べて、壁画をお月見らしい雰囲気にしてみましょう。
⑮すすき
お月見にはすすきが付き物ですが、それが何故かご存知でしょうか?
秋の実りを神様に感謝するとともに、来年の豊作を願うために行われていたのがお月見であり、すすきは稲穂に見立てられていたと言われています。
以上、9月の壁面製作としておすすめの壁画作品集でした!
このように9月には伝統的な月見、敬老の日といった行事があります。
季節を感じるイベントとして、それらを盛り上げる意味でもイベントに関連したものを壁画に組み込みやすいと言えます。
また、どんどん秋が深まっていく時期でもあるため四季の移り変わりを楽しむ時期として、秋の草花や生き物を取り入れ自然を身近に感じるのも良いでしょう。
暑さも油断できない時期ではありますが、壁画を通して秋を実感できるきっかけにしてみてくださいね。