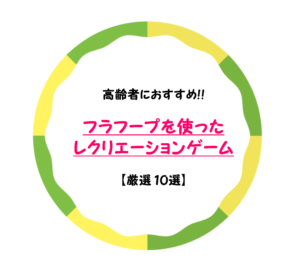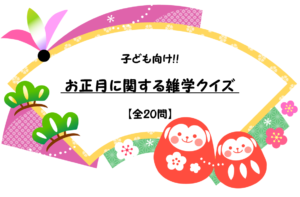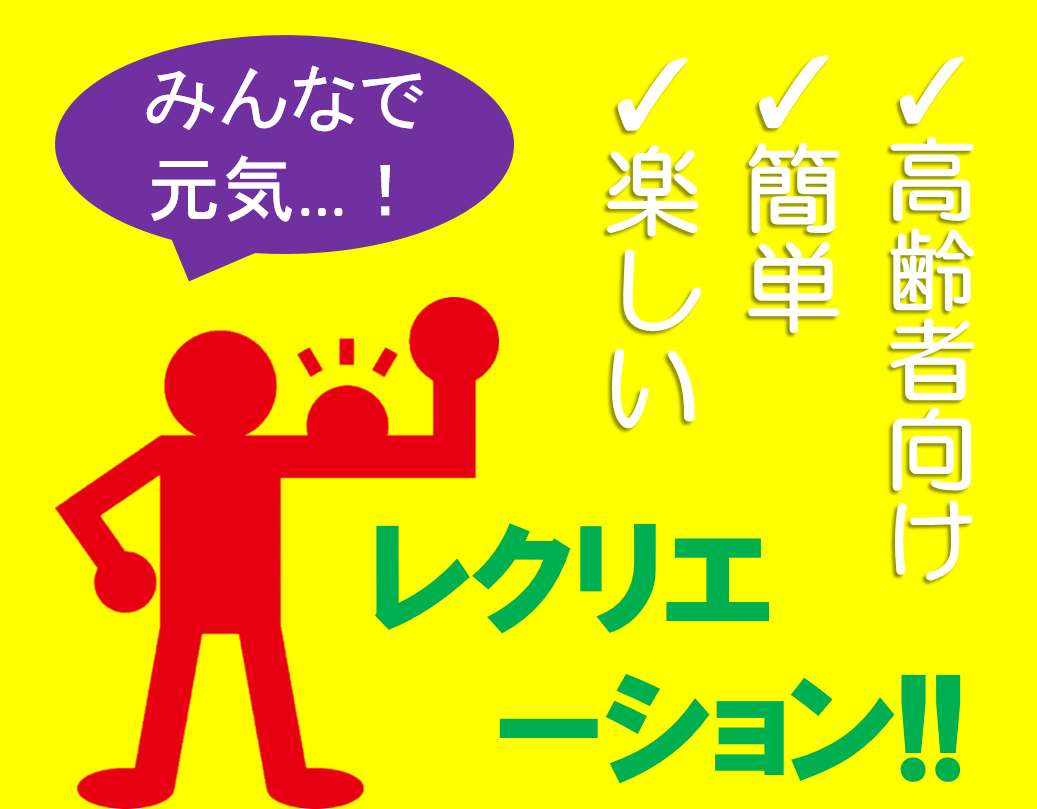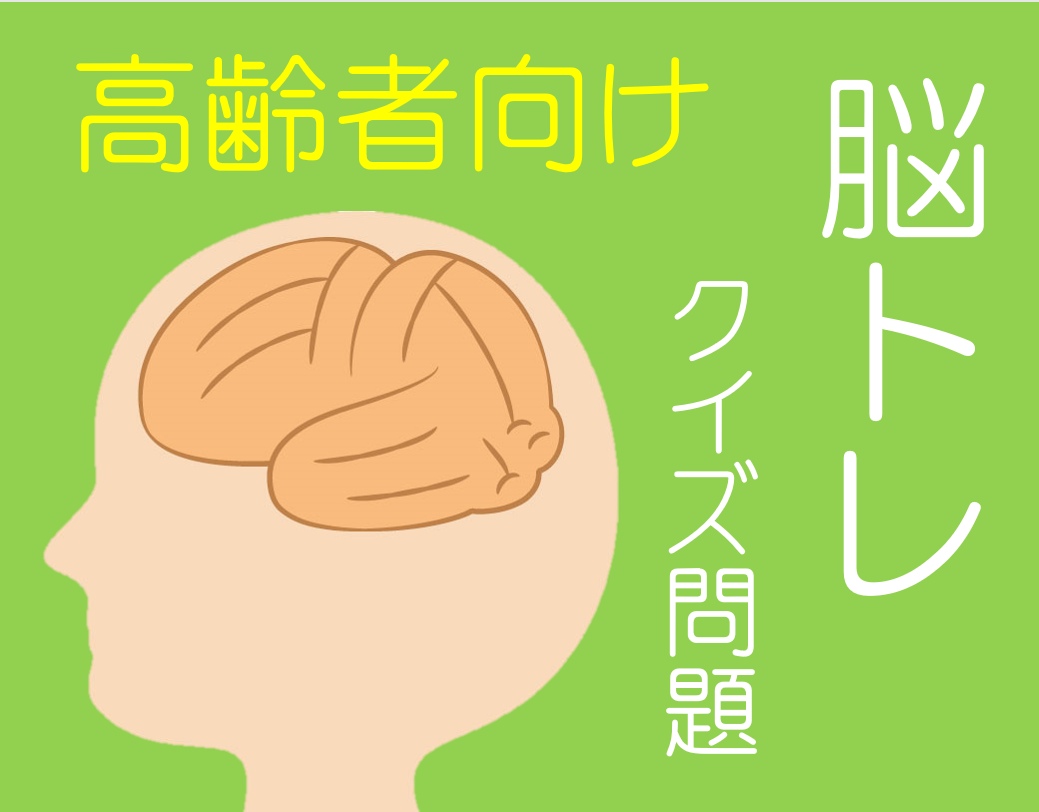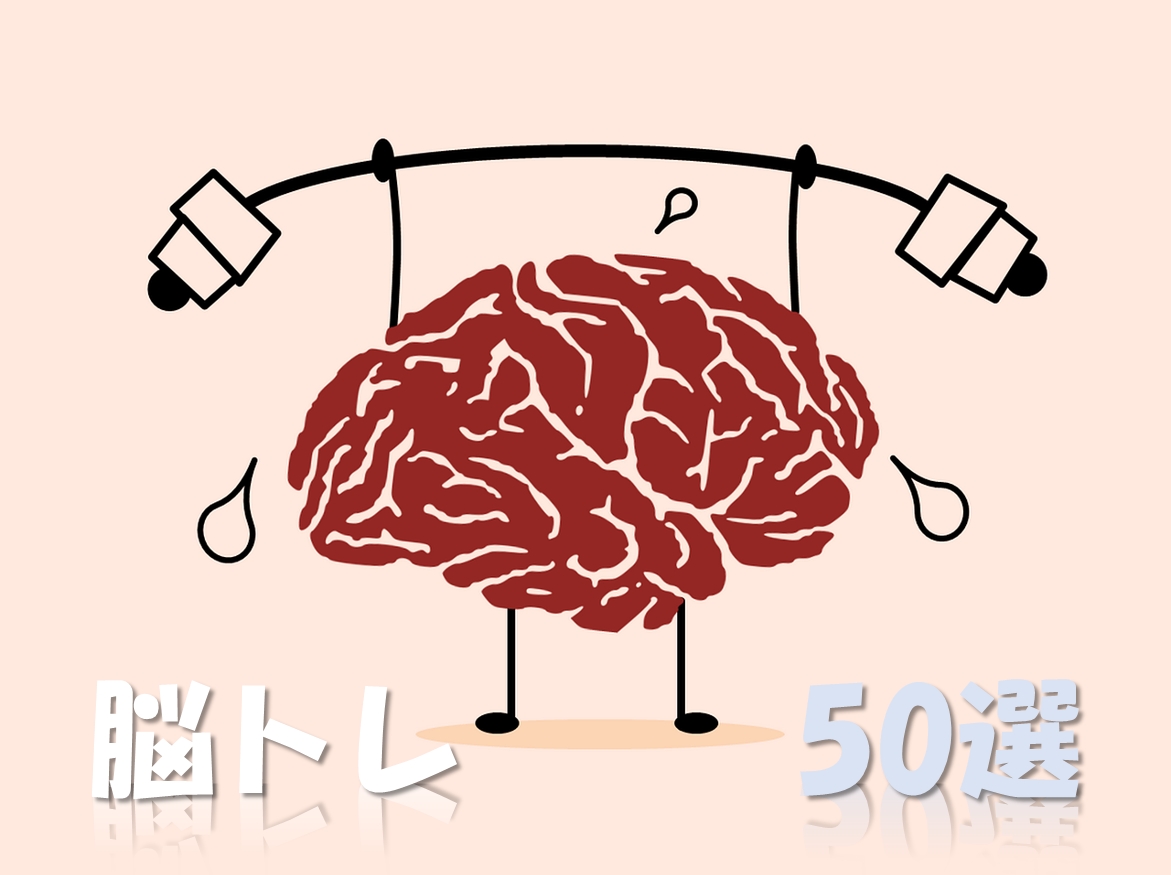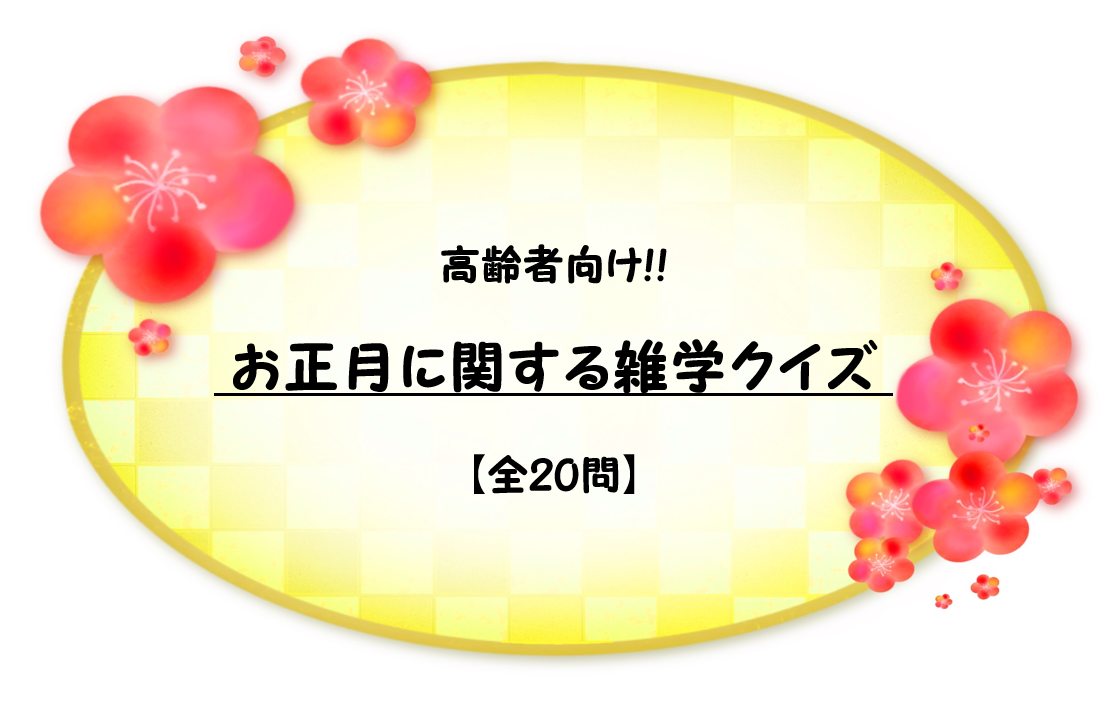
1年の始まりであるお正月は、初詣に行ったりお節料理を堪能したり楽しいイベントが盛りだくさんです。
皆様は、お正月をどのようにお過ごしでしょうか?
今回は、お正月がより楽しくなる雑学クイズ20問をご紹介します。
三択式となっていますので正解だと思うのを選んでください。お正月雑学クイズを解きながらより楽しいお正月を過ごしましょう!
それでは、お正月雑学クイズスタートです。
目次
高齢者向け!!お正月に関する雑学クイズ問題【前半10問】
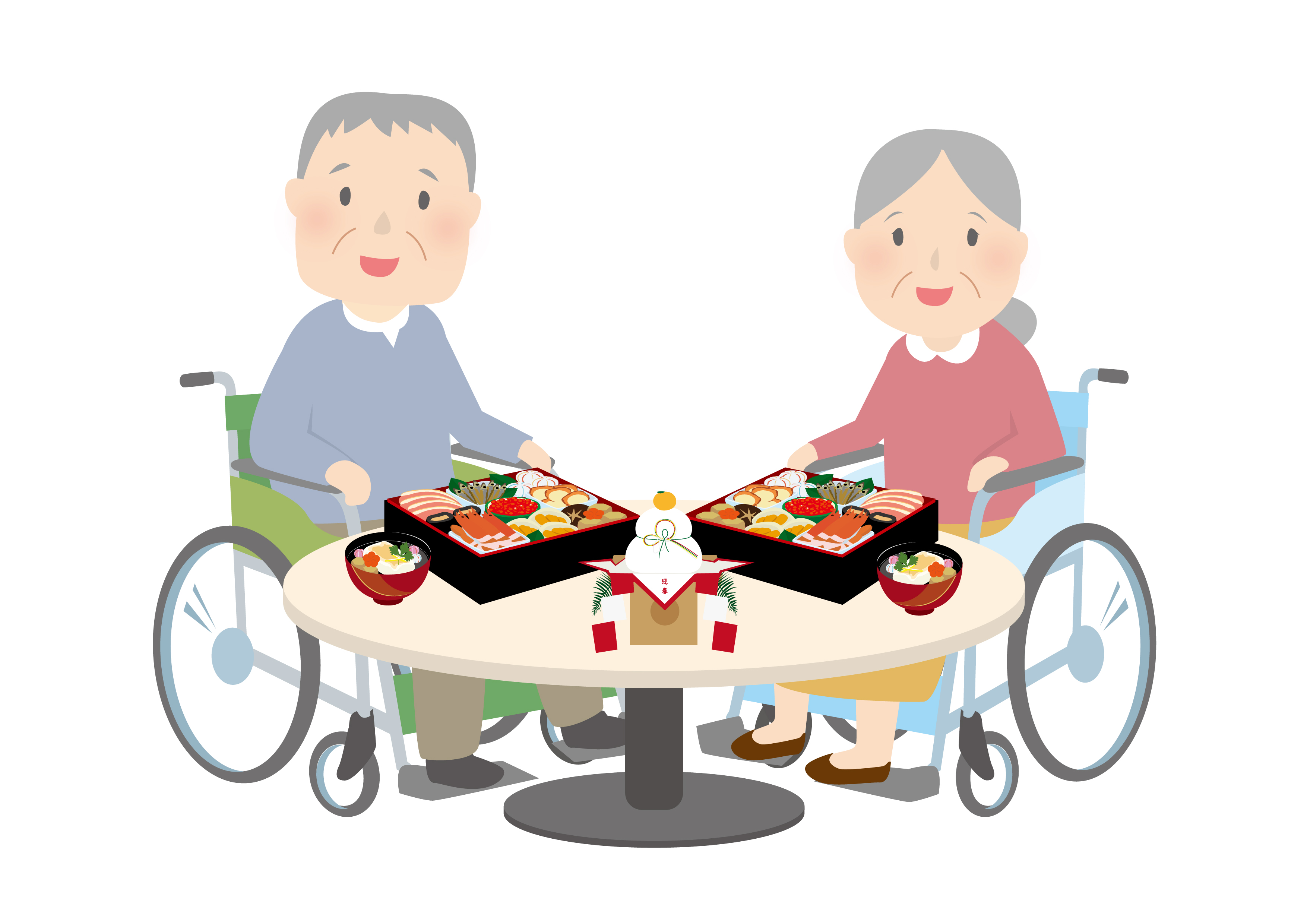
第1問
お節料理に入っている黒豆にはどんな効果があるでしょうか?
① 魔除け
② 子孫繁栄
③ 豊作祈願
第2問
元旦から三が日の間に飲む薬酒の事をなんというでしょうか?
① 養老酒
② お屠蘇(おとそ)
③ 山酒
第3問
次のうち正月に飾るものはどれでしょうか?
① 月見団子
② ひな人形
③ 門松
第4問
年賀状は12月何日までに投函すると元旦に届くでしょうか?
① 12月25日
② 12月24日
③ 12月23日
第5問
鏡開きは1月何日でしょうか?
① 1月5日
② 1月21日
③ 1月11日
第6問
注連飾り(しめかざり)などの正月の飾りにみかんなどのオレンジ色の果物が使われているのは何故でしょうか?
① 厄を払う為
② 家が代々栄えるように
③ 不老長寿
第7問
元旦の日の朝に昇ってくる太陽の事を何というでしょうか?
① 初日の出
② 元旦日
③ 春陽
第8問
初詣をするようになったのは何時代からでしょうか?
① 平安時代
② 明治時代
③ 江戸時代
第9問
現在は、お年玉と言ってポチ袋にお金を入れて子供に配ったりしていますが、昔はお金ではなく何を渡していたでしょうか?
① 餅
② 薬草
③ 飴
第10問
正月の遊びである凧揚げはどこの国から伝わったものでしょうか?
① 韓国
② オランダ
③ 中国
高齢者向け!!お正月に関する雑学クイズ問題【前半の答え】

第1問 ① 魔除け
答えの解説
黒豆と言えば名前の通り黒いですよね。
黒色には魔除けの効果があるといわれています。
黒豆は魔除け以外にも、「まめ」=勤勉と健康という意味があります。
いつまでも、健康に働けますようにという願いが黒豆には込められています。
第2問 ② お屠蘇(おとそ)
答えの解説
お屠蘇(おとそ)は、平安時代に中国から伝わった薬酒で山椒(さんしょう)や防風(ぼうふう)などの薬草がはいっています。
不老長寿を願って正月から三が日の間にお屠蘇(おとそ)を飲むと良いとされています。
第3問 ③ 門松
答えの解説
門松は正月を代表する飾りです。
松に3つの竹を立て梅の枝をあしらったものを2つ並べたものです。
江戸時代から門松は広まったとされ、向かって左の門松は雄松(おまつ)、右は雌松(めまつ)と呼ばれています。
第4問 ① 12月25日
答えの解説
年賀状を元旦に届けたい場合は12月25日までにポストに投函しておくと良いです。
新年の挨拶が始まりの元旦に届いたら嬉しいですよね。
第5問 ③ 1月11日
答えの解説
1月11日は鏡開きを迎えるので飾ってある鏡餅は下げて、お汁粉や雑煮にして食べましょう。
神様にお供えした鏡餅を食べる事で新しい生命力を授けてもらえるといわれています。
第6問 ② 家が代々栄えるように
答えの解説
注連飾りや鏡餅にはよく、みかんなどのオレンジ色の果物が使われていることが多いと思います。これは橙(だいだい)と呼ばれており、家が代々栄えて欲しいという願いを込めて飾られています。
みかんが飾られていることが多いですが、よく似た色なら他の柑橘類でも代用が可能です。
第7問 ① 初日の出
答えの解説
元旦の朝に昇ってくる太陽の事を初日の出といいます。
初日の出を祈る儀式は、江戸時代から広まった風習で厄払いと1年間の幸福を祈る為に行われた儀式だといわれています。
第8問 ② 明治時代
答えの解説
初詣の歴史はまだ浅く、文化が広まったのは明治時代からです。
それまでは、家で静かに新年を迎えていました。
午後0時になると初詣に行くという方も多いですが、元旦に食事を家族で終えてから皆で揃って行く方も多くいらっしゃいます。
第9問 ① 餅
答えの解説
昔は、お金ではなく小さな丸い餅を沢山作り子供たちや親戚などに配っていました。
それが江戸時代になり商人が奉公人の子供に餅の代わりにお金をあげるようになりそれが広まり現在にも風習が残っています。
第10問 ③ 中国
答えの解説
平安時代に敵陣から脱出するために用いられてきましたが、次第に遊びとなり子供だけではなく大人にも親しまれています。
続いて後半です!!
高齢者向け!!お正月に関する雑学クイズ問題【後半10問】
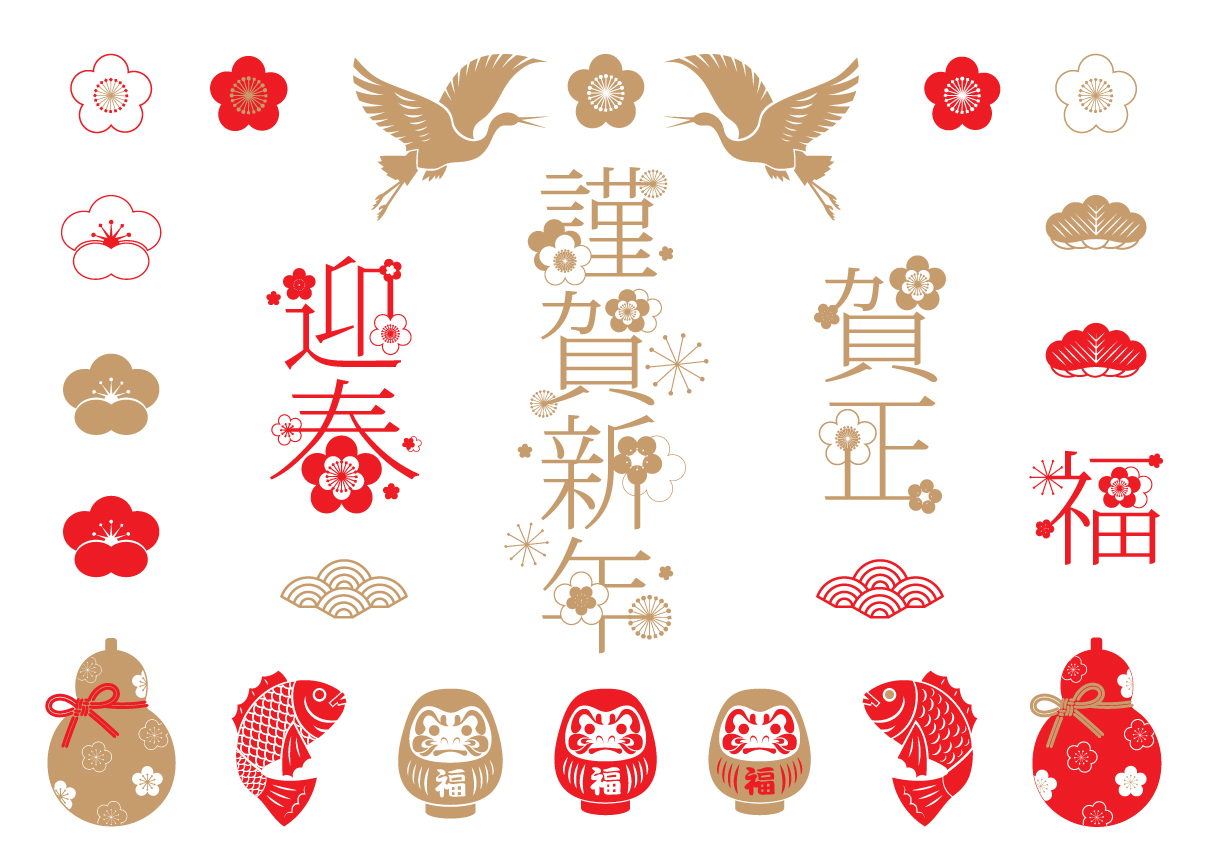
第11問
新年初めて見る夢の事を何というでしょうか?
① 初夢
② 新夢
③ 祝い夢
第12問
正月料理で疲れた胃を休める為に1月7日に食べられるものは何でしょうか?
① 薬膳スープ
② 七草粥
③ 梅おむすび
第13問
目隠しされた人が目・鼻・口などのパーツを並べて顔を作る昔ながらの正月遊びとは?
① 双六(すごろく)
② 百人一首
③ 福笑い
第14問
寒中見舞いは1月何日からになるでしょうか?
① 1月8日
② 1月7日
③ 1月5日
第15問
正月のお節料理にも使われている鯛は七福神のどの神様が抱えている魚でしょうか?
① 大黒天(だいこくてん)
② 恵比須(えびす)
③ 寿老人(じゅろうじん)
第16問
招き猫があげている右手は何を招くとされているでしょうか?
① お金
② 客
③ 健康
第17問
新年の挨拶回りをすることを何というでしょうか?
① 年賀回り
② 年始回り
③ 新年回り
第18問
お正月休みが明けた後に、新年最初に仕事を行う事を何というでしょうか?
① 新年始め
② 御用始め
③ 年賀始め
第19問
鏡餅を乗せている木の台は何と呼ばれているでしょうか?
① 三方(さんぼう)
② 神棚
③ 供え台
第20問
正月料理にはぶりが欠かせない京阪神地方で、正月に使ったぶりを1月20日に食べつくす風習を何というでしょうか?
① ぶり正月
② 魚正月
③ 骨正月
高齢者向け!!お正月に関する雑学クイズ問題【後半の答え】

第11問 ① 初夢
答えの解説
新年で初めて見る夢の事を初夢といいます。
富士山を初夢で観ると縁起が良いとされている為、枕の下に富士山の絵を入れる風習もありました。
第12問 ② 七草粥
答えの解説
正月が終わる1月7日、疲れた胃を休める為に食べられるのが七草粥です。
七草粥には、「ほとけのざ・せり・ごぎょう・はこべら・すずしろ・すずな・なずな」の七つの薬草が入っており、これを食べて1年間病気をしないようにと願いを込めて食べます。
第13問 ③ 福笑い
答えの解説
昔ながらの正月の遊びとして知られている福笑いとは、おたふくなど顔の輪郭だけが描かれた紙の上に目隠しされた人は、目・鼻・口などのパーツを手探りで並べて顔を完成させる遊びです。
出来上がった顔を観て笑い福を呼び込みます。
「笑う門には福来る」ですね。
第14問 ① 1月8日
答えの解説
寒中見舞いは、松の内が終わる1月8日以降となります。
もし、年賀状の返事が遅くなり相手の家に着くのが1月8日以降になる場合は、寒中見舞いとして出すようにしましょう。
寒中見舞いは、寒い時期に相手を気遣う便りとして出されています。
第15問 ② 恵比須(えびす)
答えの解説
正解は恵比須様です。
七福神の恵比須様が鯛を抱えていることから、鯛は豊漁の象徴とされています。
鯛を食べる事は「めでたい」とされている為、お正月にかかわらずお祝い事にもよく食べられている魚です。
第16問 ① お金
答えの解説
縁起物として売られている招き猫は、右手をあげている猫と左をあげている猫がいて、どちらを買えば良いか悩みますよね。
一般的にお客様を招くのは左手をあげている招き猫で、右手をあげているのはお金を招くとされています。
お店の店先に招き猫を飾ると縁起が良くて商売繁盛につながるかもしれませんね。
第17問 ② 年始回り
答えの解説
年始回りは1月2日~1月7日の松の内の間に済ませます。
挨拶をする時には、タオルやせっけんなどの品物を用意し「御年賀」と書かれた紙をかけて持参します。
しかし、新年早々に挨拶に行くのは大変ですよね。
その為、年始回りの代わりになっているのが年賀状です。
第18問 ② 御用始め(ごようはじめ)
答えの解説
お正月休みが明けた後、その年の最初に仕事を行うことを御用始めといいます。
民間の企業では、三が日の明けた4日を御用始めとするところが多いです。
第19問 ① 三方(さんぼう)
答えの解説
鏡餅などの供え物を乗せている木の台は、三方(さんぼう)と呼ばれています。
三面に穴が開いているので三方といいます。
神聖なもので昔は一般の人が使うことは、禁じられていました。
第20問 ③ 骨正月
答えの解説
正月にぶりが欠かせない京阪神地方では正月行事の納めの日となる1月20日に正月に使ったぶりを骨まで食べつくす風習があり骨正月(ほねしょうがつ)と呼ばれています。
20日は正月に迎えた神様がそれぞれの場所へ戻る日でもあります。
地域によっては19日の夜に小豆ご飯や尾と頭がついた魚をお供えするところもあります。
これで高齢者向けお正月クイズは終了です!
いかがでしたでしょうか?
日本に住んでいて長年お正月を経験しているのに初めて知る事もあり大変、勉強になります。
特にお年玉が昔は食べ物だったという事には驚きました。
クイズを通してお正月の楽しい気持ちに浸って貰えたのなら嬉しいです!
是非、コミュニケーションにも役立ててくださいね。